▪️
事業がやめられません!― 事業見直しの仕組みづくりとスクラップの必要性 ―
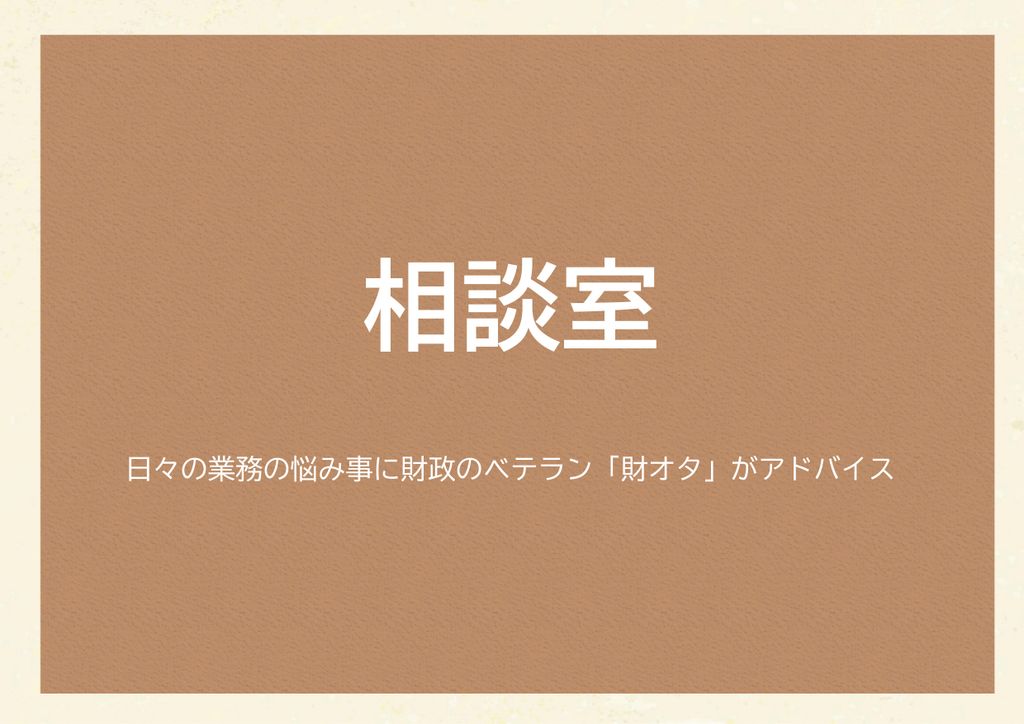
Q 毎年の予算編成のなかで原課の担当者と「この事業はそろそろやめて(見直して)もいいのでは」「そうですね、また検討します」と会話するのですが、その先の議論が進みません。どんな仕組みが必要でしょうか。
個別の事業であれば、その事業の経緯、実施期間、現状、他の事業との比較、国等の政策の変化などを客観的に示し、財政課の懸念を明確に伝えることが大事です。一方、見直しには、実現しやすいタイミングもあり、検討時間も必要なことから、過去の指摘事業であれば、予算要求時期によらず「この宿題の回答が得られない場合は予算は付けない」旨を事前予告し、仮に新規事業が検討されているなら、新規事業と廃止事業の関係性を踏まえて内容を整理すれば良いと思います。
また、補助金であれば、時代とともにその必要性や支援内容が変化することが多いため、当初から期限(例:3年)を定め、必要性に応じその期限を更新するという手法をとれば、長くても期限末には終了すべきかの判断が可能です。
財政課には、一般財源を最適配分する努力が求められます。そのためには、いずれの要求にも責任感を持ち、公平・公正に判断すべきですが、無理なく事業を見直すルールを導入し、業務とストレスの軽減を図ることも大事です。
Q そもそも、事業のスクラップや見直しがなぜ必要なのか、原課の納得を得られる説明ができません。前年と同じように事業継続することは望ましくないのですか。
自治体の予算編成とは、地域の課題解決に向け、一般財源の最適配分をすることです。ですから、現在実施している事業や予算規模が地域の最適解であれば、「前年通り」でよろしいと思います。
しかし、時が経てば経費は増嵩し(特に維持管理費)、課題は変化し、国は新しい施策を打ち出します。地域住民等からは新たな課題への新規要望も出ます。よって、単なる「前年通り」は、地域課題解決に向けた最適解ではありません。
また、普通交付税の交付団体は一般財源の大幅な増加は見込めず、ふるさと納税等の独自に稼げる自主財源があったとしても、財源に見合った支出とするため予算編成時の事業や経費の見直しは必須作業となります。
このようなことから、事業のスクラップは、持続可能な地域の実現に向けた大切な作業です。「前年通り」の要求が妥当と思える時は、その課題や背景に変化がなく、今の時代にあった適切な要求の結果です。その違いを意識しましょう。
相談室テーマ大募集!
日々の業務の中で抱く悩み事や疑問に、財政のベテラン「財オタ」がアドバイスします。
読者アンケートフォームからお送りください。
回答者

高岡市
長久洋樹さん
高岡市生活環境文化部長。財政課長時代に、高岡市財政健全化緊急プログラムを牽引、予算編成工程の工夫で、収支均衡予算を達成し、財政課職員の残業時間も大幅に改善。総務省(地方公共団体の経営・マネジメント強化事業)アドバイザー。中小企業診断士。NPO法人T.upの副理事長・事務局長。
給湯室の投稿を見る
日々の業務のちょっとした疑問や困り事は会員同士で聞いちゃいましょう!
「わざわざ他自治体に照会するほどじゃないけど、気になっていること」
「誰に相談したら良いのか分からないこと」
など、会員限定ホームページ内の”給湯室”で匿名投稿ができます。時には財オタも回答します。
