▪️
DX関連経費の予算査定、どうする?
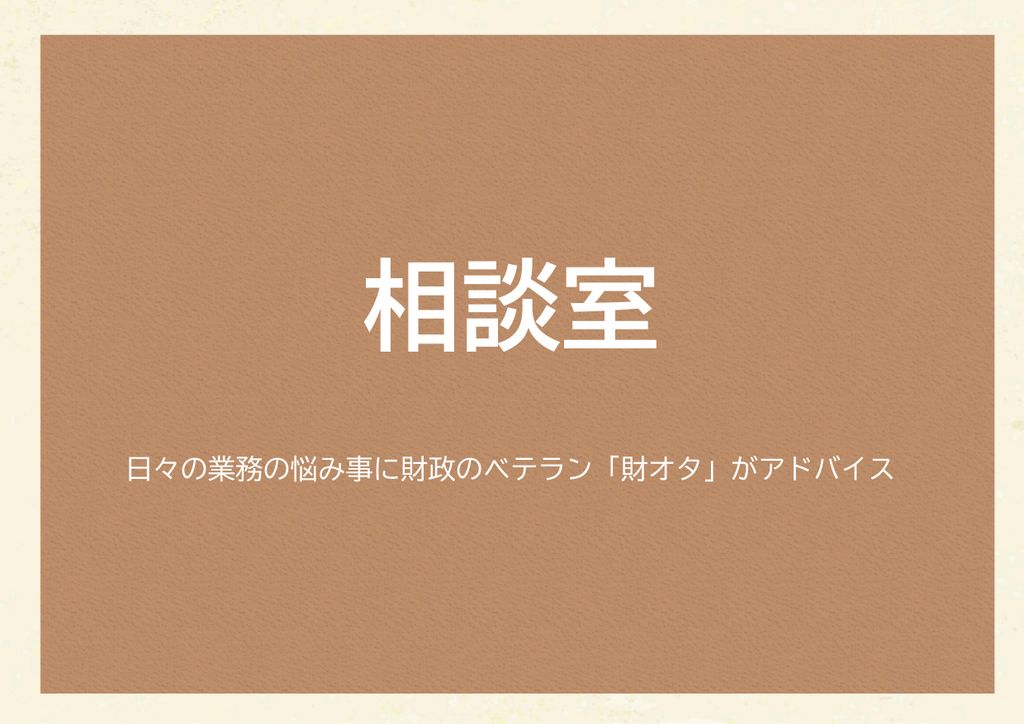
Q 毎年各課から様々なDX関連経費の計上がありますが、ランニングコストがかかるものも多く、費用対効果だけ見ると先送りせざるを得ません。どのような視点で査定すべきでしょうか。
DX関連経費は初期導入費よりもランニングコスト(クラウド利用料・保守
費)が大きな比重を占める傾向にあり、「費用対効果」の即効性だけで判断すると、どうしても先送りになりがちです。そこで「長期的視点」「政策整合性」「リスク回避」で査定する必要があります。
①長期的視点 1〜2年では費用超過でも、5年スパンでは職員の削減、事務経費の削減など「内部コスト圧縮」が見込める場合があります。 ②他自治体・国方針との整合性 総務省の「自治体DX推進計画」など、国が推奨する方向性に沿ったものは、外部評価にも耐えやすく、交付金・補助金・地方債の活用余地があります。 ③リスク回避 セキュリティ強化や災害対応力向上といった「見えにくい便益」も査定に含め、予防投資として位置づけます。
査定に当たっては、財務的効果(コスト削減率)ばかりでなく、住民サービス(待ち時間短縮、満足度向上)、内部効率(削減時間、人件費換算額)、成長・学習(データ活用度や職員のスキルアップ)などをスコア化して優先順位を決めるといいでしょう。
Q 特に自治体の内部事務に対しては、職員の減少も見据えて業務効率化を進めるべきなのですが、住民サービスに直結しないため、コスト投入しづらいと感じています。
内部事務のDXは住民に直接見えにくいため、査定で後回しにされがちですが、人口減少に伴って職員数の減少が見込まれる自治体組織にとっては不可欠です。
①住民サービスへの間接効果として説明 内部文書処理の自動化などは職員時間を住民窓口対応や相談業務に振り向ければ、住民に見える改善につながり、財政的な優先度をつけやすくなります。 ②費用対効果を人件費換算で見える化 あるシステムの導入で年間○○時間削減=△△人分(年□□百万円)の工数削減、と数値換算すると、投資意義が明確になります。 ③段階的・試行的な導入 一気に全庁展開ではなく、モデル課で試行し効果を検証 → 翌年度以降に展開、という流れを予算査定の条件とすることで、過大投資を避けつつ推進できます。
北見市の「書かないワンストップ窓口」、奄美市の「電子契約」、WiseVine社の予算編成DXシステムなどはいずれも「内部効率」や「財務効果」の観点で高く評価できる事例です。
これらはDXへの前向きな投資が自治体経営の未来をより確かなものにすることを示しています。
相談室テーマ大募集!
日々の業務の中で抱く悩み事や疑問に、財政のベテラン「財オタ」がアドバイスします。
読者アンケートフォームからお送りください。
回答者

元足立区
定野 司
1979年足立区に入区。財政課長時代の2002年に包括予算制度を導入。2022年、財ラボ代表理事就任。主な著書に「自治体の財政担当になったら読む本」(学陽書房)などがある。
給湯室の投稿を見る
日々の業務のちょっとした疑問や困り事は会員同士で聞いちゃいましょう!
「わざわざ他自治体に照会するほどじゃないけど、気になっていること」
「誰に相談したら良いのか分からないこと」
など、会員限定ホームページ内の”給湯室”で匿名投稿ができます。時には財オタも回答します。
最近の投稿
【回答募集中!】【1号随契の基準額引上げに伴う専決区分などの金額見直しについて】
地方自治法施行令の一部を改正する政令が令和7年3月25日に閣議決定されたことに伴い、当自治体の財務規則のうち1号随契の基準額を令和7年度から引き上げました。
1号随契の基準額が引きあがったということは、予算執行、支出負担行為及び支出命令などの専決区分、その他、財務規則で設けている各金額の基準、また、入札や工事検査などの金額の基準も、同じ割合で引き上げても問題ないのではないかと思いますが、近隣他自治体で、1号随契以外の基準額を変更した例を確認できませんでした。
他の自治体の例を参考に、令和8年度から財務規則などを改正したいと考えており、既に、専決区分を変更した自治体がありましたら、改正の前後表のご提供をいただけないでしょうか。
また、改正予定の場合、考え方などご教示いただけると幸いです。
